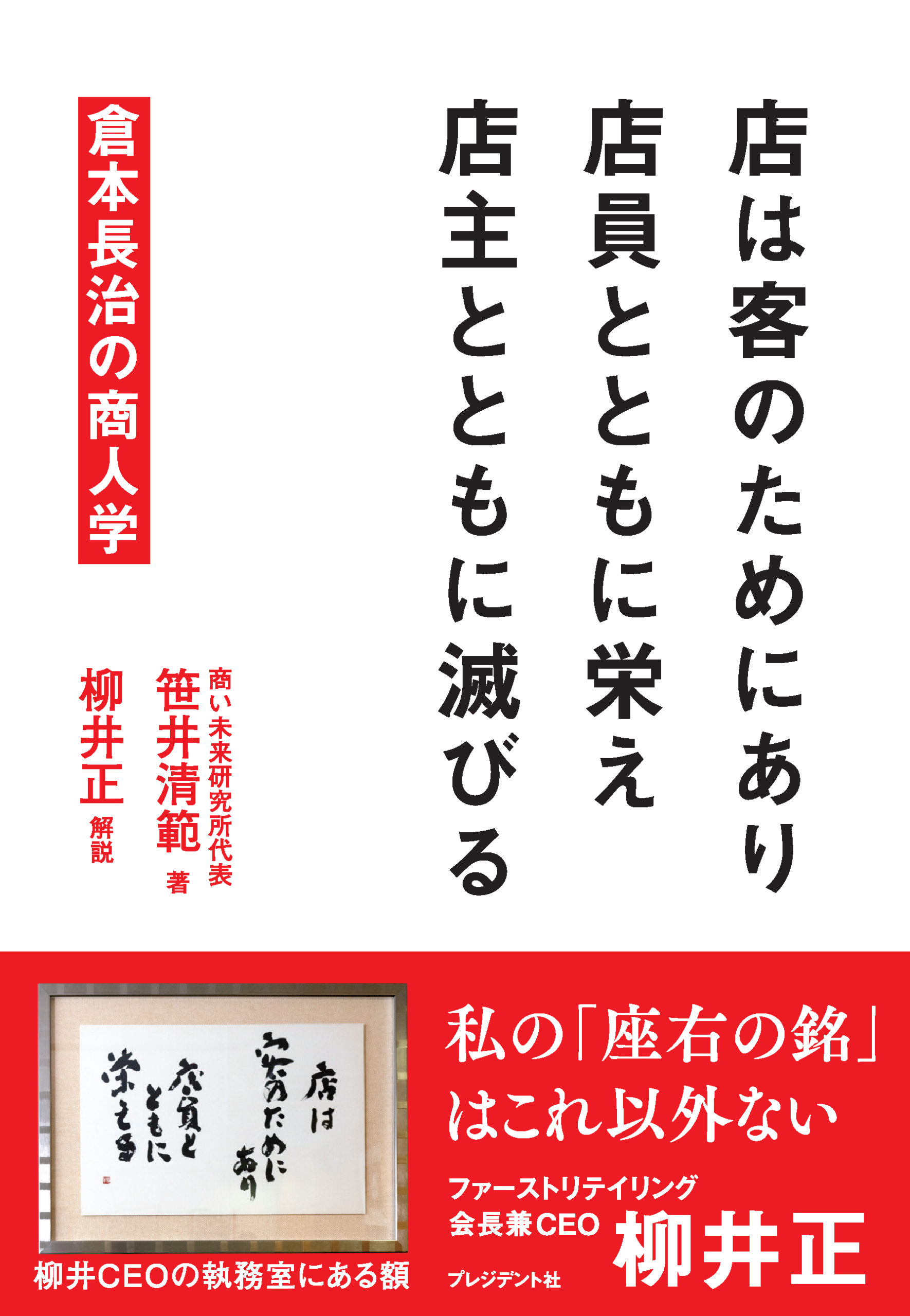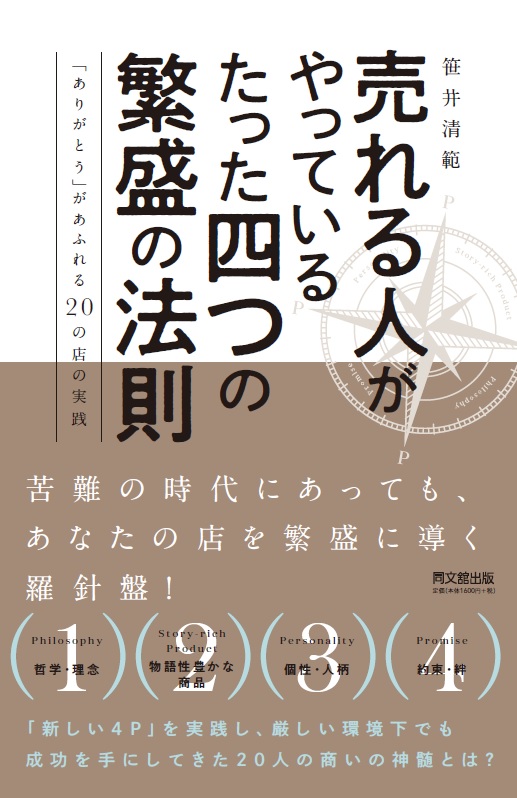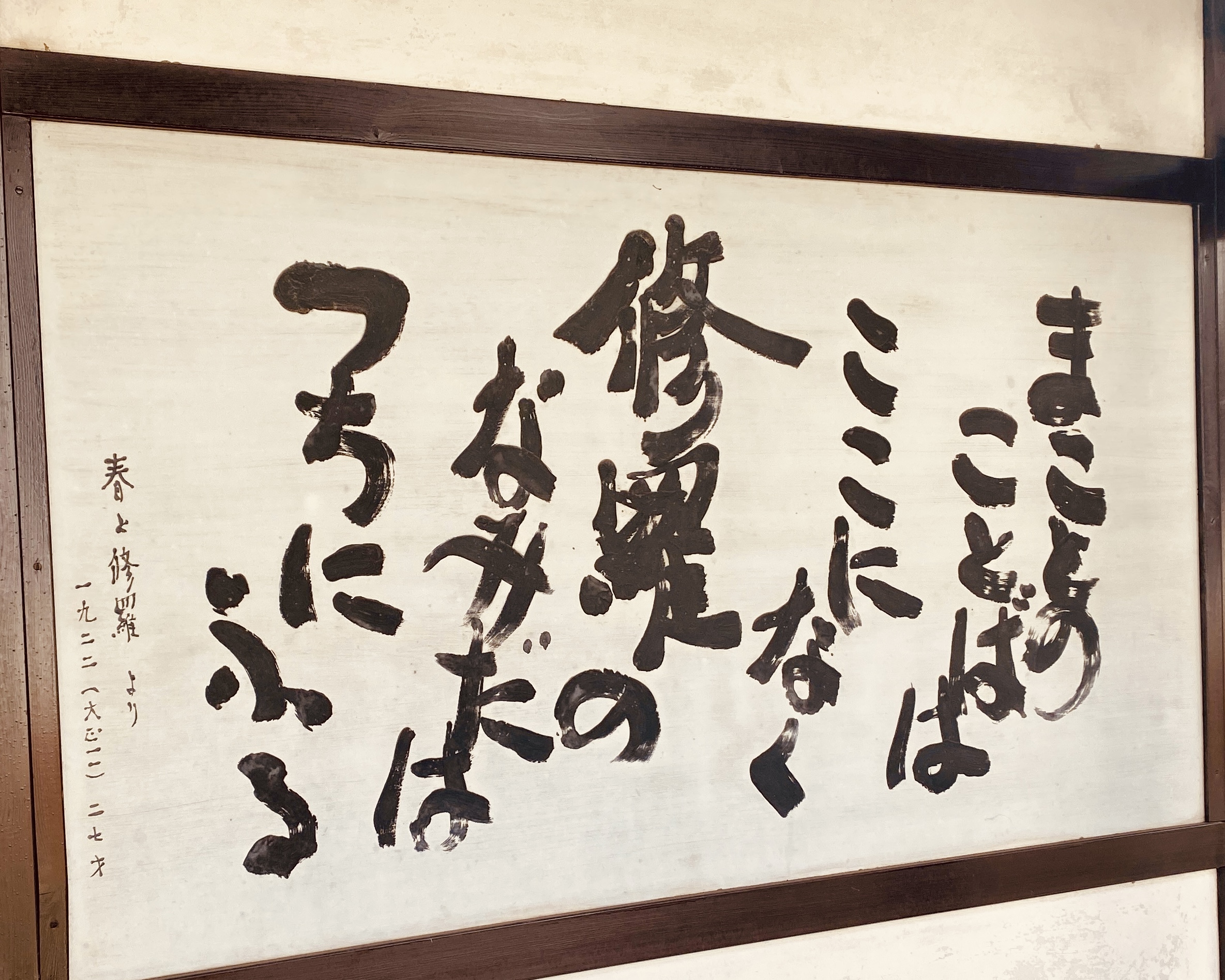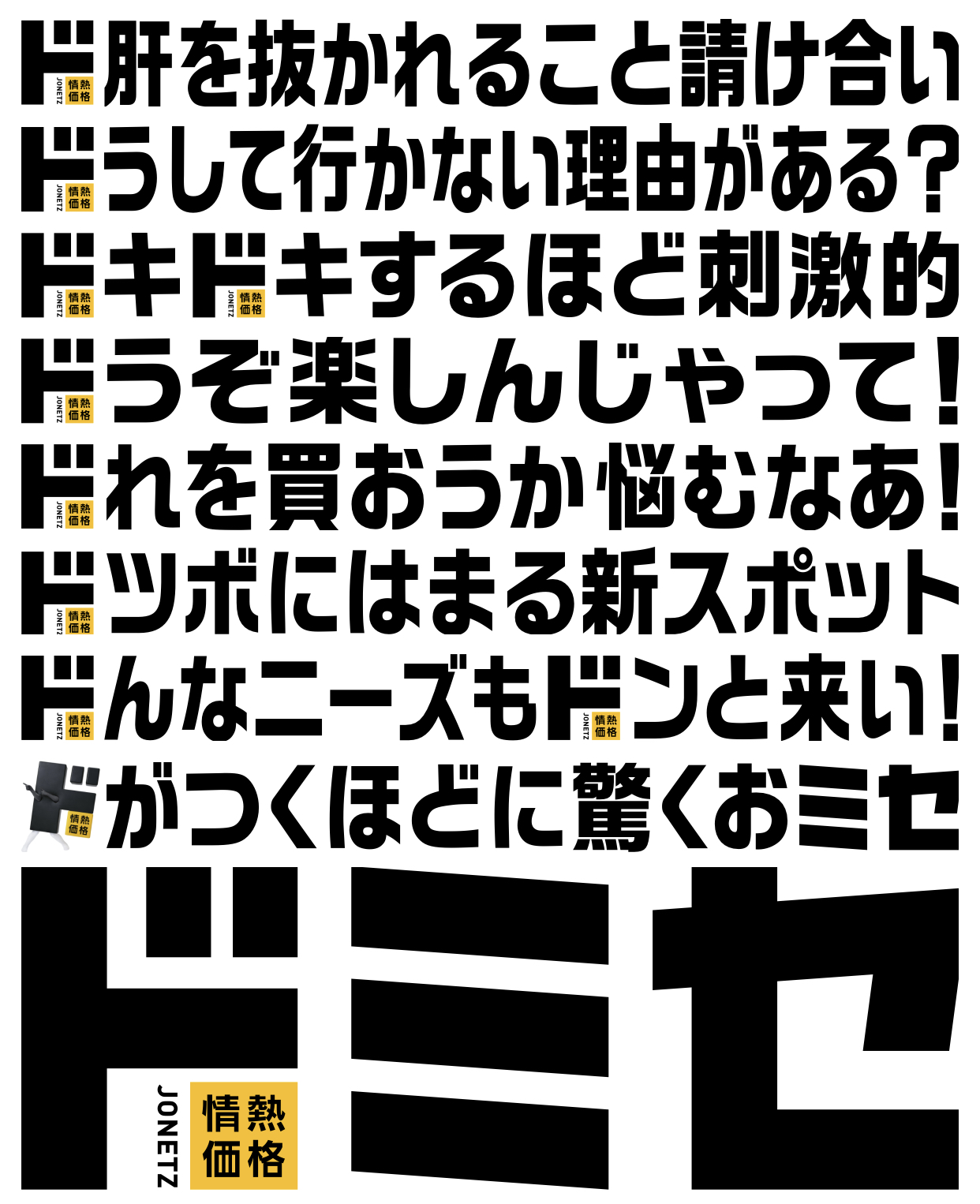北の大地で32年間という短い命を、土を耕すことと絵を描くことに捧げた一人の画家がいました。その人、神田日勝の遺した作品は今もその輝きを失わず、多くの人たちの心をとらえています。私もその一人で、東京ステーションギャラリーで特別展「大地への筆触展」が開催されたときも訪れました。
日本を代表する農民画家、神田日勝は1937年に家族と共に7歳で拓北農兵隊として、北海道十勝鹿追町に移住。厳しい開拓生活を送りながら、兄の影響で油絵を描きはじめました。その題材は農耕馬や牛といった農民の暮らしを主題とし、短い画歴ながら常に自己を表現できる画風を求め続けたことで知られています。
ただし、ベニヤ板にペインティングナイフで絵の具を刻みつけるような筆致は変わることはありませんでした。対象に迫る構図のとり方、大胆な色彩表現などの特徴は、同じく農民画家として画業を始め、短い画歴で早世したゴッホの点描画を想わせます。
しかし本人は農民画家と呼ばれることを好まず、自らを「画家である、農家である」と区別して語っていたといいます。この特別展のコピーも「ここで描く、ここで生きる」と画家である自分と農家である自分を分けています。
展示は、初期のモノクロームな色彩を特徴とする作品から始まり、日勝の画歴と画風の変遷をなぞる形で導かれ、最後は絶筆となった「馬」で締めくくられていました。ベニヤ板そのままの背景に頭部から半身だけ描かれた馬は、未完成であるがゆえに観る者に生命の躍動と生への執着を感じさせます。
過労がたたり日勝は腎盂炎による敗血症で32歳で亡くなり、「馬」は後脚を描かれることはありませんでした。このときの日勝はどんな思いで最期を迎えたのでしょうか。「どう云う作品が生まれるかは、どう云う生きかたをするかにかかっている」とは日勝の言葉です。
画家にとって生きかたと作品が連動するものであるように、あらゆる人にとっても生きかたと仕事は連動するものだと、未完の馬を観ながら思いました。たとえば、商として何をどう売るかは、人としてどう生きるかと同じです。そうした営みを通して、関わる人たちの記憶に残り続ける――それが人がその命をかけるに値することを教えてくれました。