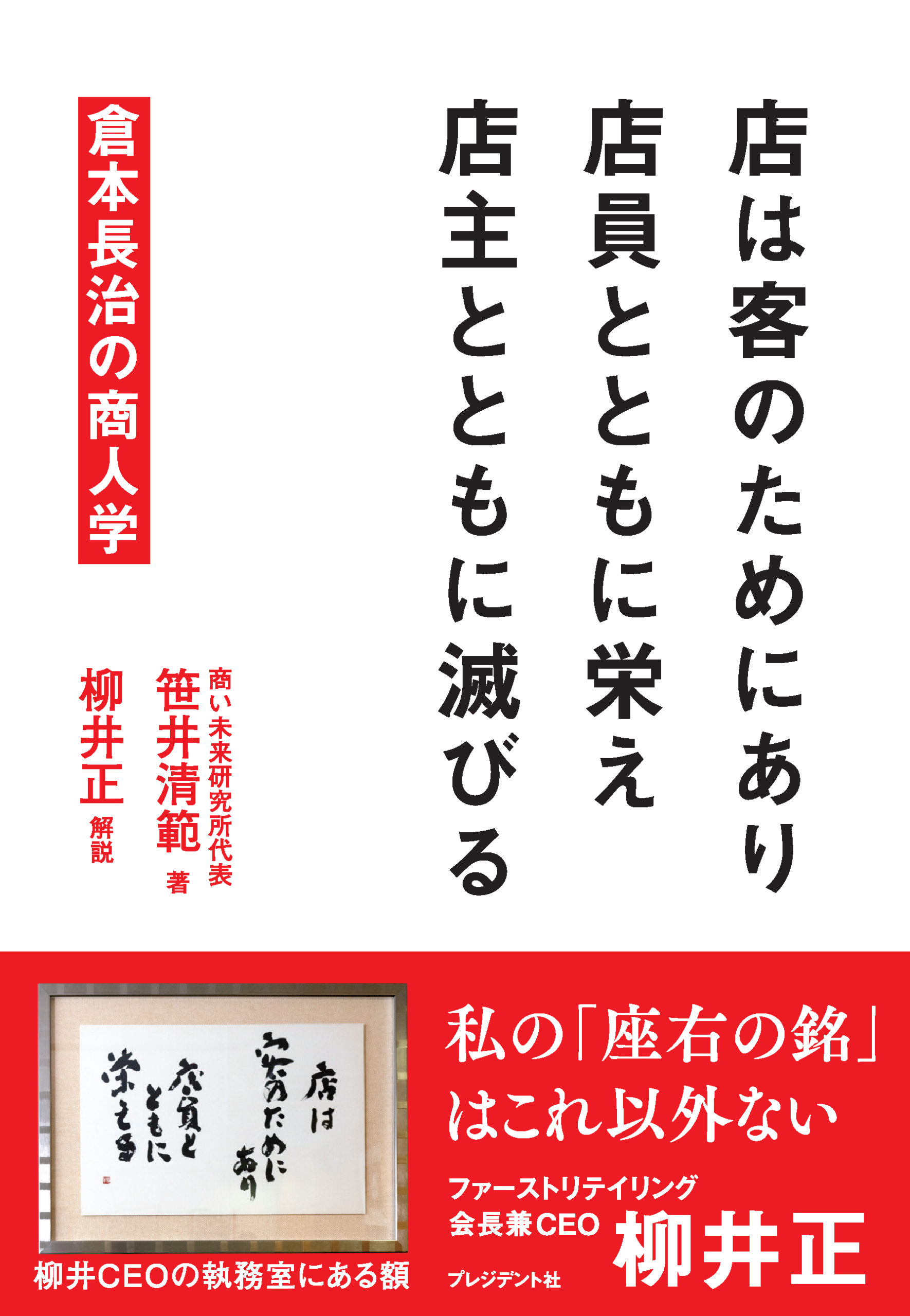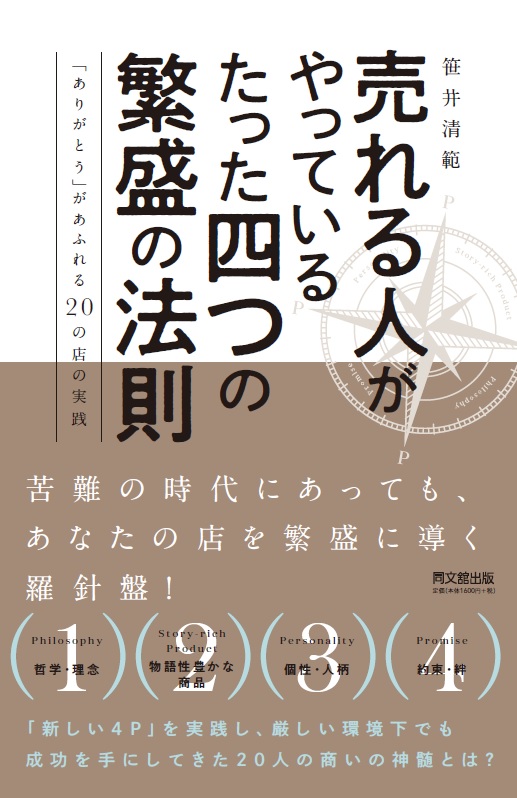「おじいちゃん」
「うん?」
「なんで 八でも十でもなくて 用九なの?」
「八だとちょっと足りないし 十だと多いからね」
「でも お店にはモノがいっぱいあるよ 用十にすればよかったのに」
「何事もほどほどがちょうどいいものだよ」
これは、台湾の漫画家、阮光民さんの「用九商店」(原題「用九柑仔店」)の一場面にある、祖父(創業者)と後に店を継ぐ孫が幼いころに交わした店名の由来にまつわる会話。用九商店は食べものや日用品が揃う、台湾の昔ながらの「よろず屋」で、そこを舞台に人と人の絆を描いた物語です。
都会で働く孫のもとに祖父が倒れたと知らせがあり、店を閉じるために帰省したところから物語は始まります。彼の仕事は不動産会社の社員として、再開発のために旧市街の古い家々を地上げすることでした。
店の片づけに取りかかろうとしていると、そこに店の常連の一人がやってきます。主人公が彼に「オレ店を閉めないほうがいいのかな」と問うと、常連は24時間空いているコンビニの便利さに触れつつも、「ここ(用九商店)には居心地の良さがある」と話しはじめました。
「懐が心もとない人はツケ払いができる。身寄りがいない人はここに来れば話し相手がいる。子どもは放課後にここで両親の帰りを待てばいい。仕事を探している人には店の掲示板に求人がある。知りたいことがあればここで聞ける。ちょっと立ち寄っただけの行商人も休憩ついでに商売してもいい……店は人々につながりを与える場所だったんだ」
その夜、主人公は祖父の部屋を片づけました。そこには、家族のアルバム、幼いころの落書き、柱に刻まれた背丈のしるし……。家というのは記憶を保存するメモリーディスク。もし家を売ったり、店を人に譲ったら、祖父と自分、そしてお客様の思い出も消すことになると思い至り、「だったら、オレが明かりをともそう。そう決めた」と決意するのでした。
それからのドラマは、ぜひ本書をご覧ください。私もそうするつもりです。また、本書は各話の扉に、タイトルと共に一文が添えられています。たとえば第二話。
「客がどこで何を買うかは自由
だから仕入には細心の注意が必要なのだ」
そう、まさに仕入れは商人そのもの。そこには人柄や個性が反映されるものです。