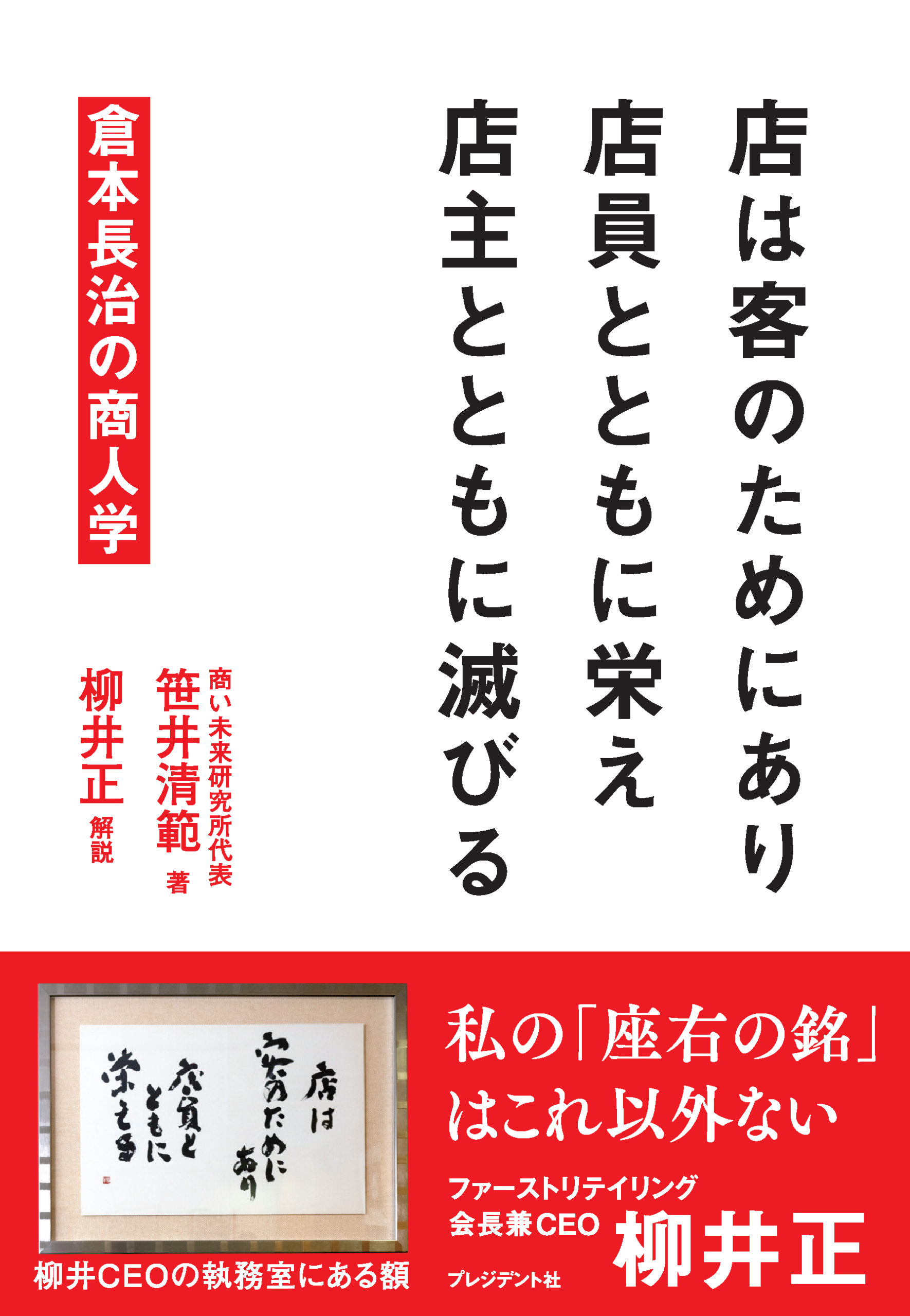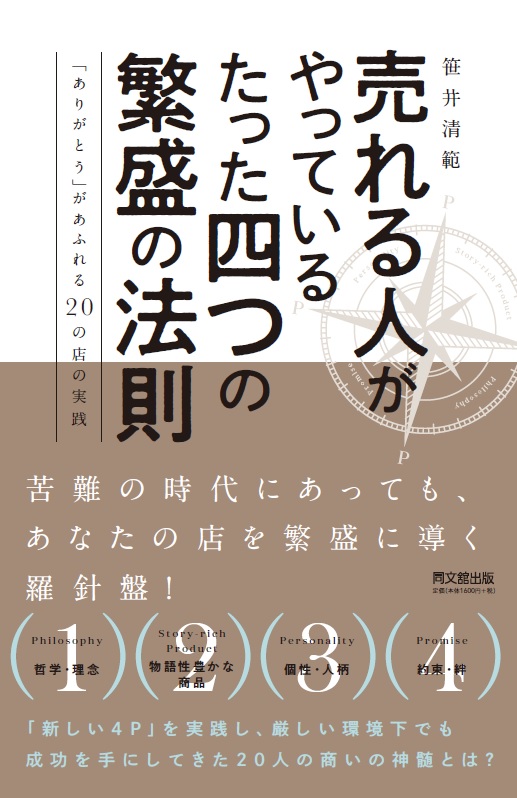日本の伝統芸能や武道の世界でなじみ深い「稽古」という言葉。単なる練習や反復のことではなく、「古(いにしえ)を稽(かんが)える」という意味を持ちます。つまり、先人の知恵や精神に立ち返り、そこから自らの技と心を磨き上げる営みです。商いの世界にも、この稽古の精神は生きています。
大阪府堺市の豆腐店「安心堂白雪姫」の店主、橋本太七さんと妻の由起子さん。惜しまれながら店を閉じましたが、稽古という言葉から思い浮かぶのは、真っ先にこのお二人です。
創業は1984年。以来、量産や価格競争とは一線を画し、豆腐本来の味とおいしさを追求し続けてきました。そんな二人の商いの原点には、ある師との出会いがありました。
師から学んだ「一番」の意味
太七さんが「人生の師父」と仰ぐのは、金沢の持ち帰り寿司店「芝寿し」創業者、故・梶谷忠司さん。船乗りだった太七さんが由起子さんに心配をかけまいと商いを学ぶ決意をし、芝寿しに研修で入ったのが縁の始まりでした。
当初3カ月のつもりが、12年の歳月を過ごす中で、梶谷さんの商売哲学を肌で学びます。それは、商業界創立者・倉本長治が提唱した「店は客のためにある」という理念を、日々の現場で徹底的に実践することでした。
ある日、梶谷さんからの手紙が太七さんに届きます。そこには、「創造と挑戦で大阪一美味しい豆腐を造ってください。一番とは一番儲ける店ではなく、一番お客様に喜ばれる店のことです」と記されていました。
さらに、「最高の原料を使い、水にも金をかけなさい。一見馬鹿らしいようだが、その正直さが客の舌に響く」との一節。派手な宣伝や値引きではなく、愚直に品質を磨くことこそが信頼を育むという教えです。

この教えは、まさに稽古の精神と重なります。日々の仕込みは早朝4時から始まり、夜9時まで続きます。その一つひとつの工程に、昨日より今日、今日より明日と、一歩でも前に進もうとする心構えが宿ります。太七さんは北海道産の良質な大豆や、会員制でしか手に入らない天然にがりと出会い、試作を1年重ねた末に看板商品「白雪姫豆腐」を完成させました。その過程もまた、稽古そのものでした。
日々の積み重ねが困難を越える力に
稽古の本質は、繰り返す中で形に心を込め、やがて形を超えて心が形を導く境地に至ることです。橋本夫妻にとって、それは豆腐づくりだけでなく、お客様への接し方にも表れています。
由起子さんは、全国から届く礼状や来店客一人ひとりに、心を込めた手紙を書き続けています。その筆致には、相手を思い、感謝を伝えるという、商人としての型と心が息づいています。

こうした稽古は、試練のときにも力を発揮します。由起子さんはかつて、原因不明の病で3年間寝たきりの生活を余儀なくされました。しかし、太七さんは「今日もいい顔してるね」と声をかけ続け、二人は互いを支え合いました。
この闘病の日々は、夫婦の間に強い絆と協力の型を築き、その後の商いの基礎になりました。商売も人生も、困難なときこそ稽古の真価が問われるのです。
太七さんの心に残るのは、住友グループ中興の祖・田中良夫の詩「私の願い」。「一隅を照らすものでわたしはありたい」という一節を、二人は商いの戒めとしています。これは、どんなに小さな持ち場でも、誠実に光を届けるという決意であり、まさに稽古を重ねる者の心です。
稽古とは、昨日の自分と向き合い、今日の自分を超えるための営みです。そしてそれは、技術や知識を磨くだけでなく、人としての在り方を整える道でもあります。安心堂白雪姫の豆腐がひと口で人を幸せにするのは、その背後にある何十年もの稽古の積み重ねが、味にも、姿勢にも、言葉にも染み込んでいるからにほかなりません。

商いを営む私たちもまた、日々の仕事を稽古ととらえることができます。接客、商品づくり、仕入れ、清掃——どれもが心を込めれば稽古になり、積み重ねればお客様に伝わります。そして、その稽古をやめない限り、商いは必ず成長していくのです。