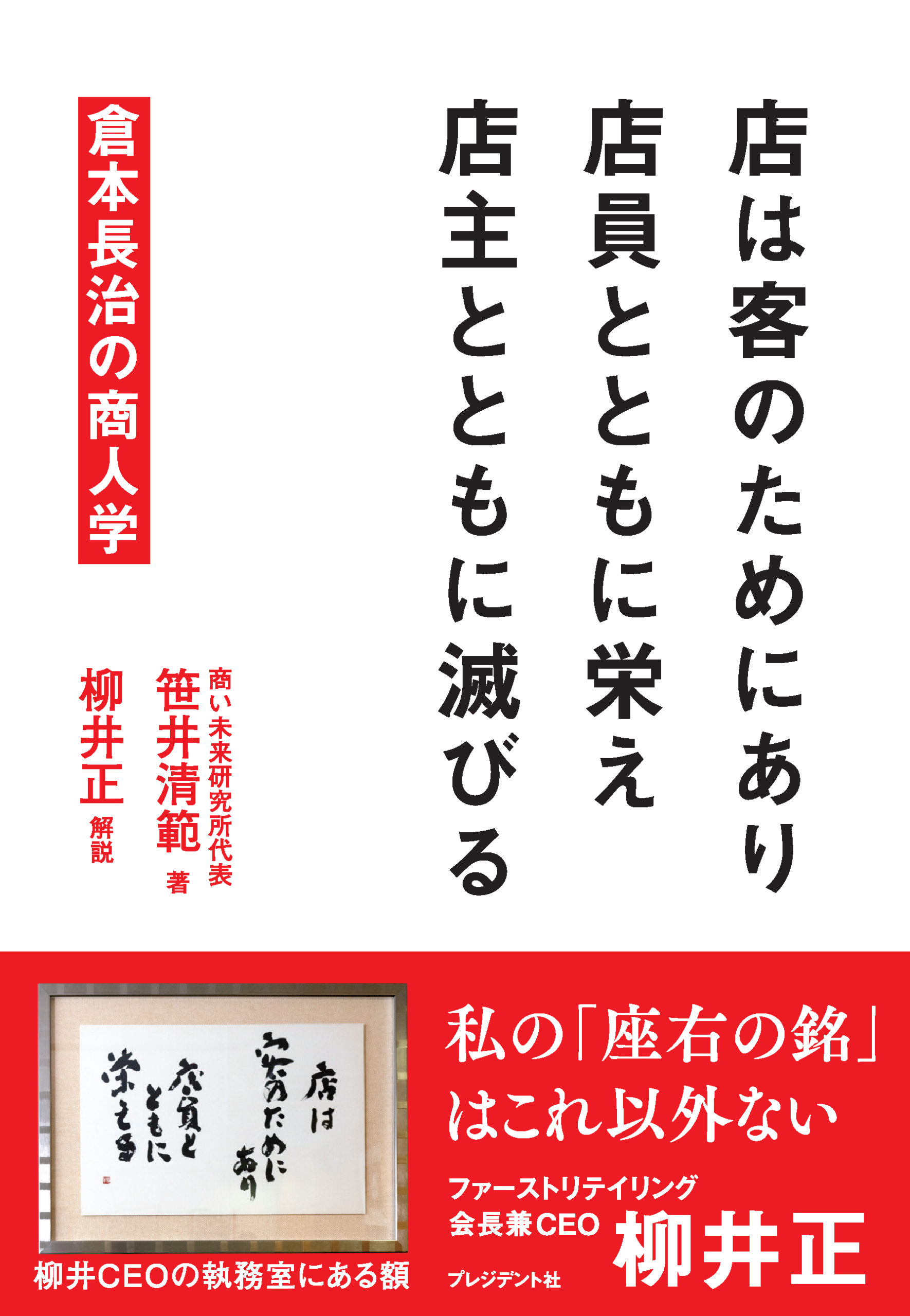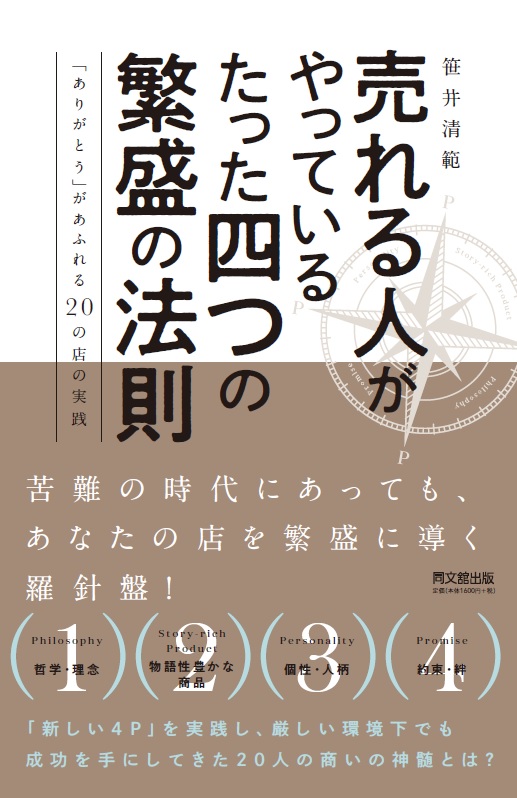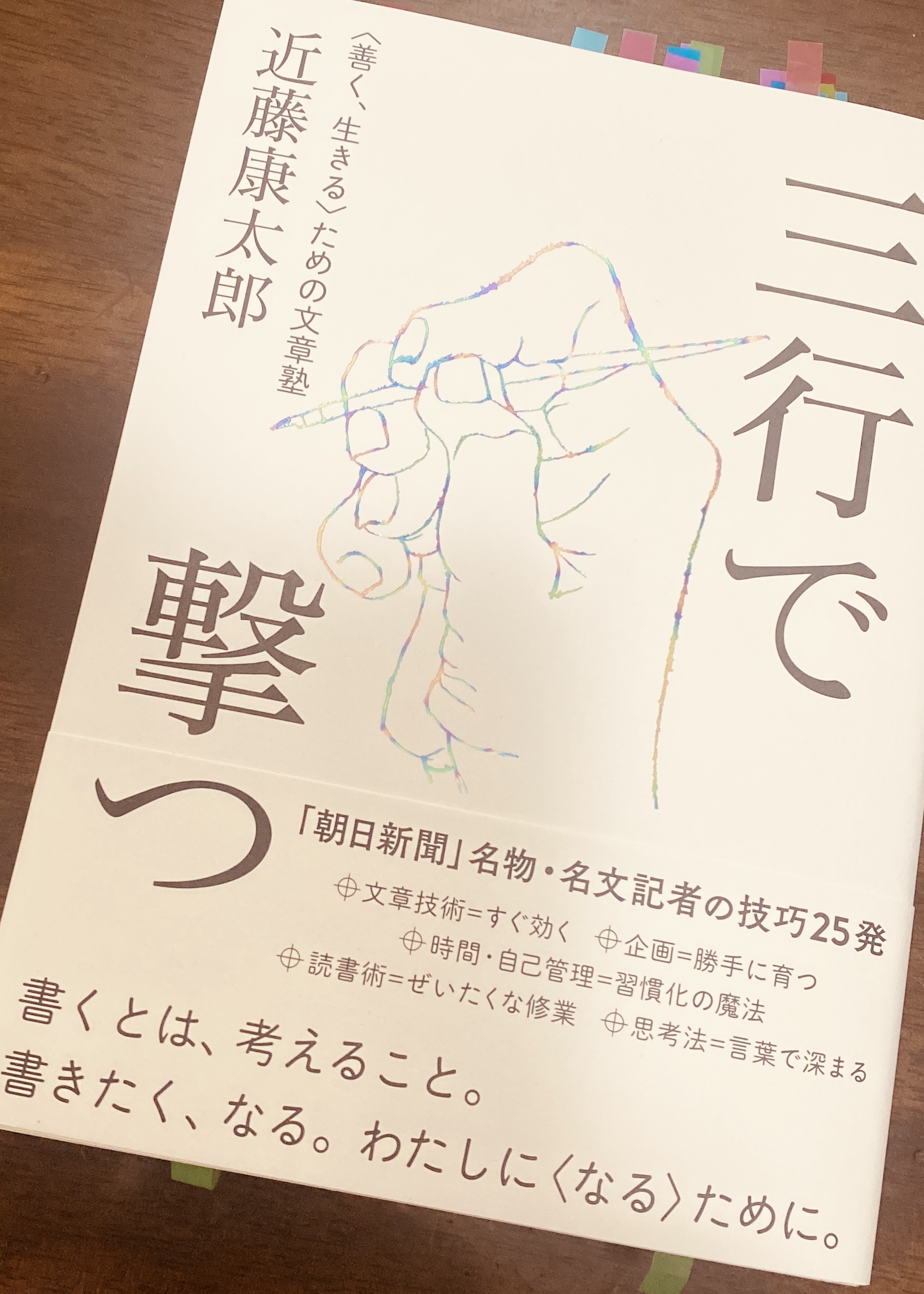小さな店にとって、PRはどこか遠い世界の話に聞こえがちです。人手も時間も資金も足りない。まして専門知識など持ち合わせていない――そう感じている商人は、けっして少なくないでしょう。しかし、本書『片手間PR術』が教えてくれるのは、PRとは特別な技術でも、一部の才能ある人の専売特許でもなく、日々の商いの延長線上にある営みだという事実です。
副題に『取材が絶えない「商店街の小さなたいやき屋」の広報戦略』とあるように、著者の辻井啓作さんは、東京・阿佐ヶ谷の商店街で「たいやき ともえ庵」を営む店主です。けっして大資本でも、有名店出身でもありません。それでも数多くのメディア取材を受け、行列の絶えない店をつくり上げてきました。その歩みは、理論や成功法則をなぞったものではなく、失敗と試行錯誤を重ねながら積み上げてきた実践の歴史です。
読み進めるほどに、そのことがよくわかります。メディア対応の基本、取材されやすい情報のつくり方、日常の出来事をニュースに変える視点、無理なく続ける発信の考え方――いずれも「これさえやればうまくいく」といった万能解ではありません。著者自身が遠回りし、空振りを重ねながら体得してきた知恵が、具体的で現実的な言葉として語られています。
だからこそ本書は、読みながら自然と「自分の店ならどうだろうか」と考えさせられます。PRを新しい仕事として付け足すのではなく、今やっている仕事の意味を、あらためて言葉にしていく。その姿勢こそが、辻井さんの言う「片手間PR」の本質なのだと理解しました。

PRの目的はブランド化と経営のエンジン
本書の核心は、PRの先に何があるのかを明確に示している点にあります。辻井さんは、PRを単なる露出や話題づくりとして捉えていません。本書245ページで、次のように述べています。
「小さな店や会社が目指すべき方向は『ブランド化』だ。必ずしも高級ブランドになれと言っているわけではない。その店や商品が他と違う良いものだと知ってもらい、この商品なら、この店なら、と安心して買ったもらえるようになることがブランドになるということだ。(中略)これから積み上げるPR活動は、そのための大きな武器になるだろう。」
ここで語られている「ブランド」とは、背伸びした高級ブランドではありません。「この店なら大丈夫」「この人から買いたい」と思ってもらえる安心の総体です。PRは、その信頼を一つひとつ積み上げていくための手段にほかなりません。
同時に著者は、PRの力の強さと危うさにも目を向けています。本書241ページには、「PRは店や会社のことを短時間で広く知らしめるもの、経営を加速するエンジンのようなものだ。方向を間違うと、悪い方向に加速して飛んで行ってしまう」という一文があります。
PRは、使い方を誤れば経営を壊す力にもなります。注目を集めること自体が目的化し、現場が追いつかなくなる。約束できないことまで発信してしまう。著者が警鐘を鳴らすのは、いわば「PRに食われる経営」です。
だからこそ重要なのは、PRを経営のエンジンとして使いこなすことです。自分たちは何を大切にし、何を提供し、どこまで責任を持てるのか。その軸を定めたうえでPRを行う。アクセルを踏む前に、進む方向を決める。その順序を間違えないことが、本書では繰り返し強調されています。
最大のPR道具は「店」そのもの
本書の大きな読みどころの一つが、たいやき ともえ庵の見せ方を記したコラム(本書218ページ)や、「最大のPR道具は『店』そのもの」という単元(本書93ページ)です。辻井さんは一貫して、PRを広告やSNSといった手段に閉じた話として扱っていません。むしろ、店構え、商品の佇まい、焼き場の見せ方、言葉の選び方――それらすべてがメディアだと捉えています。
商品が語り、店が語り、店主の姿勢が語る。その積み重ねがあるからこそ、メディアは興味を持ち、取材に訪れます。PRとは「取り上げてもらうための工夫」ではなく、「取り上げる価値のある現場をつくること」だというメッセージが、行間から伝わってきます。
さらに本書の価値を高めているのは、「続けられるPR」に徹底してこだわっている点です。多くのPR本は、正論としてはうなずけても、現場に戻ると実行が難しいものが少なくありません。
しかし本書では、「毎日やらなくていい」「完璧を目指さない」「やめてもいい」といった、商人の呼吸に寄り添う言葉が随所に見られます。だからこそ、読後に残るのは義務感ではなく、「これならできそうだ」という手応えです。

商いを正しく伝える技術を磨く
著者が繰り返し語るのは、PRとは“自分をよく見せる技術”ではなく、“自分の商いを正しく伝える技術”だという視点です。盛ることも、飾ることもいらない。むしろ、迷いや未完成さを含めて語るからこそ、人は共感し、応援してくれる。その覚悟が、文章の端々からにじみ出ています。
「おわりに」で著者は、PRは自分で取り組んでこそ成果が上がると述べています。外注すれば効率は上がるかもしれません。しかし、店の想い、迷い、温度感まで代行することはできません。だから不器用でもいい、自分の言葉で伝える。その過程そのものが、商いを深め、ブランドを育てていくのです。
読み終えると、PRに対する構えが確かに変わります。忙しいからこそできるPRがあり、小さな店だからこそ届く言葉がある。本書は、PRを学ぶための本であると同時に、商人が自分の商いと向き合い直すための一冊。商いの現場に立つすべての人に、「それなら、明日から一つやってみよう」と静かに背中を押してくれる、実践的で誠実な良書としておすすめします。