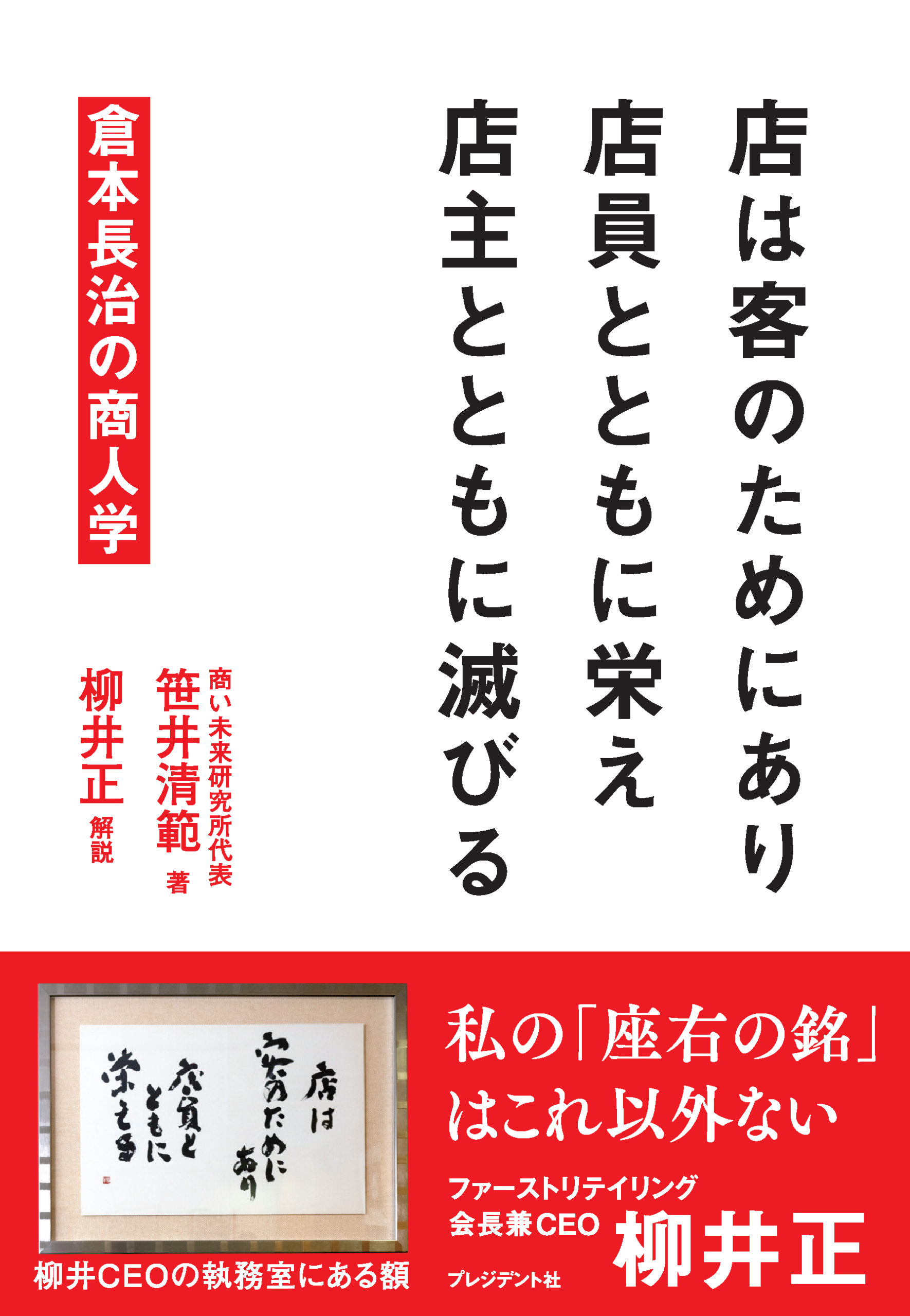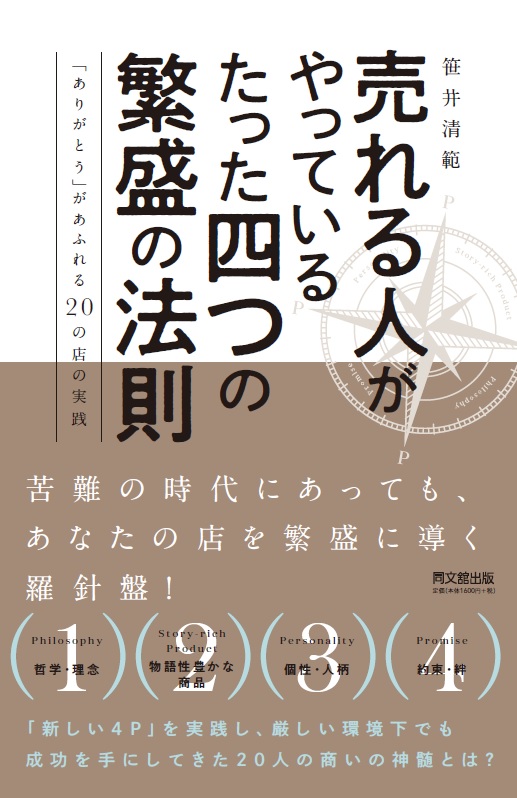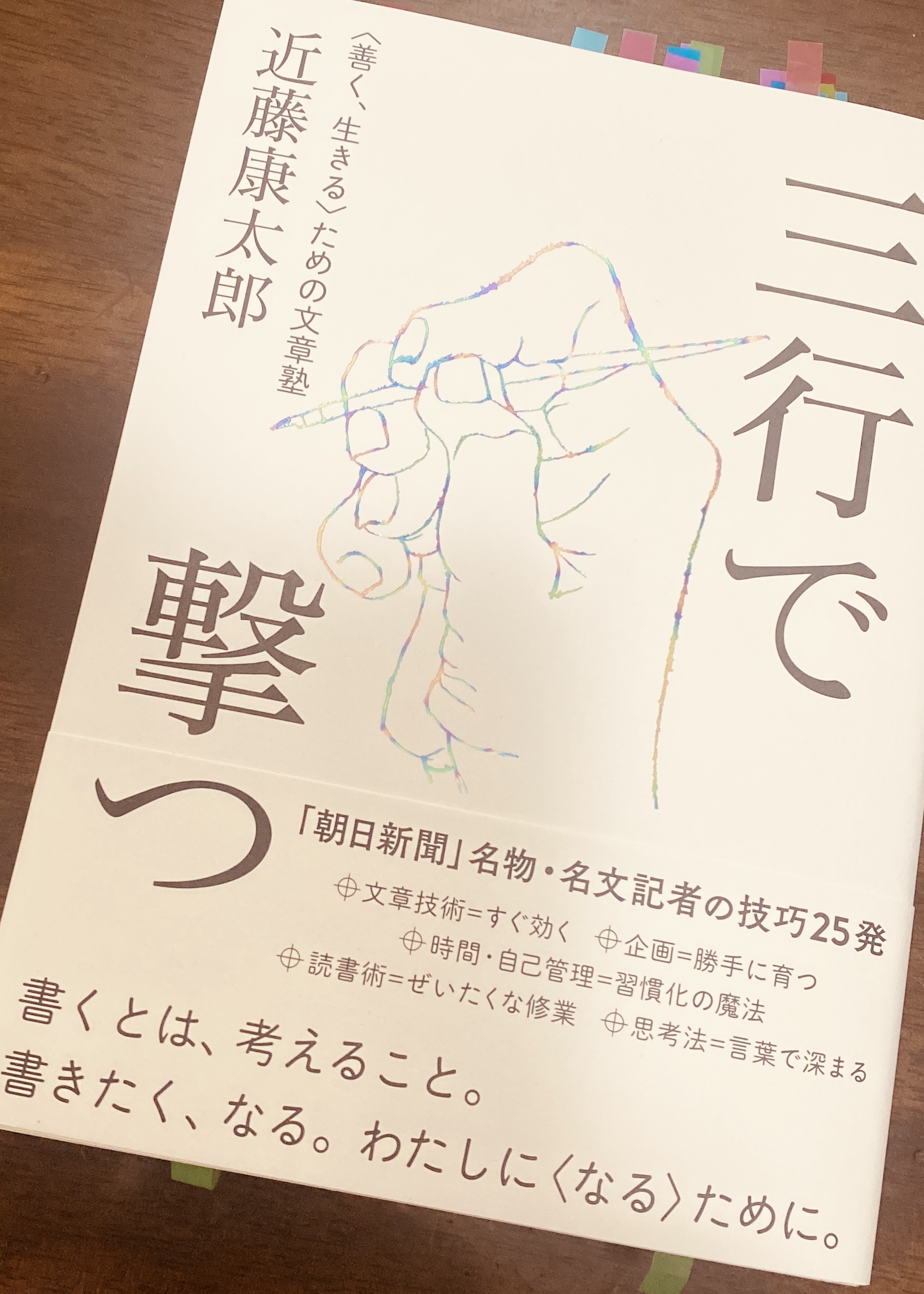朝の陸前高田--。店の扉を開けると、焙煎したての豆の香りが、まだ冷たい空気に溶けていきます。湯を注ぐと、ふわりと立ち上る香り。その一杯はただのコーヒーではありません。酒かすで発酵させた「純米酒粕発酵珈琲」は、陸前高田市の喫茶店「東京屋カフェ」の新しい挑戦の結晶です。
この一杯に至るまで5カ月。試してはやり直し、失敗を重ね、設備を整え、ようやく「これだ」と思える味にたどり着いて提供を始めたのは、2025年12月28日のことでした。珈琲豆の概念を超えた味や香り。冷めた後にもワインのような余韻が立ち上がります。
その静かな深さは、話題づくりのための商品開発とは明らかに違うものです。ここには、「なぜ商うのか」という問いに、日々向き合い続けてきた一人の商人の時間が染み込んでいます。

すべてを失った地で商いを続ける理由
2011年3月11日。東日本大震災による津波は、家も、店も、倉庫も、すべてを奪いました。剣道を続け心身を鍛えてきた小笠原修さんでさえ、「半歩下がった」と振り返るほどの惨事でした。
それでも3日後の3月14日、小笠原さんは決意します。「このまちで商いを続ける」と。自分と家族のことだけを考えれば、ほかにも選択肢はありました。実際、東京で事業を営む身内からの誘いもあったといいます。それでも残ると決めた理由は、このまちで長く商売をしてきた親のため、長年通ってくれたお客様のため、そして何より大好きな陸前高田のため。実に真の商人らしいものでした。
小笠原さんの挑戦にふれるたび、思い起こすのが「どん底に大地あり」という言葉です。これは、1945年8月9日、長崎に落とされた原爆で自らも被爆し、重傷を負いながらも救護活動に尽力した永井隆医師の言葉として知られています。「『なぜ?』『どうして?』と、自分の身を振り返っているうちは、希望は持てません。どん底まで落ちて、大地を踏みしめ、共に頑張れる仲間がいて、はじめて真の希望は生まれるのです。その希望こそ、この国の未来を創ると私は信じています」と彼は遺しています。
どん底まで落ちたからこそ、足の裏で大地を確かめることができる。小笠原さんの商いは、まさにどん底から始まりました。11カ月後、コンテナ店舗で再開。2年後、プレハブ店舗へ。2017年、ようやく中心市街地に本設移転。時間はかかりましたが、歩みは止まりませんでした。

人口が減るまちでも店にはできることがある
東京屋カフェは、祖業である婦人服店の売上を増やすための付加施設ではありません。人口が減り、高齢化が進むまちで、「暮らしに必要な場所」をつくるための選択でした。服を選び、言葉を交わし、コーヒーを飲む。その何気ない時間が、まちに残る理由になればという願いがあります。現実から目を背けず、人口減少という事実を直視し、その上で「では、このまちで商人として何ができるのか」を考え続けてきた小笠原さんならではの挑戦です。
2020年のコロナ渦中に開発した「海中熟成コーヒー」も、今回の酒かす発酵コーヒーも、共通しているのは足もとにある素材です。自分をどん底に落とした「海」。製品化されずに残されていた「酒かす」。過去を消すのではなく、引き受け、意味を与え直す。それが小笠原さんの商いです。
そんな小笠原さんには、欠かさず続けている習慣があります。毎月11日、震災の月命日に、小笠原さんは自分の考えと行いをすべて疑います。今やっていることは正しいのか。本当に、このまちの役に立っているのか、と。「危機は人間を成長させるチャンス」と語る言葉の裏には、走り続けながらも、立ち止まって自分を点検する姿勢があります。
商いは売上追求の手段ではありません。生き方そのものです。東京屋カフェの一杯のコーヒーは「なぜ商うのか」という問いへの静かで、しかし確かな答えなのです。