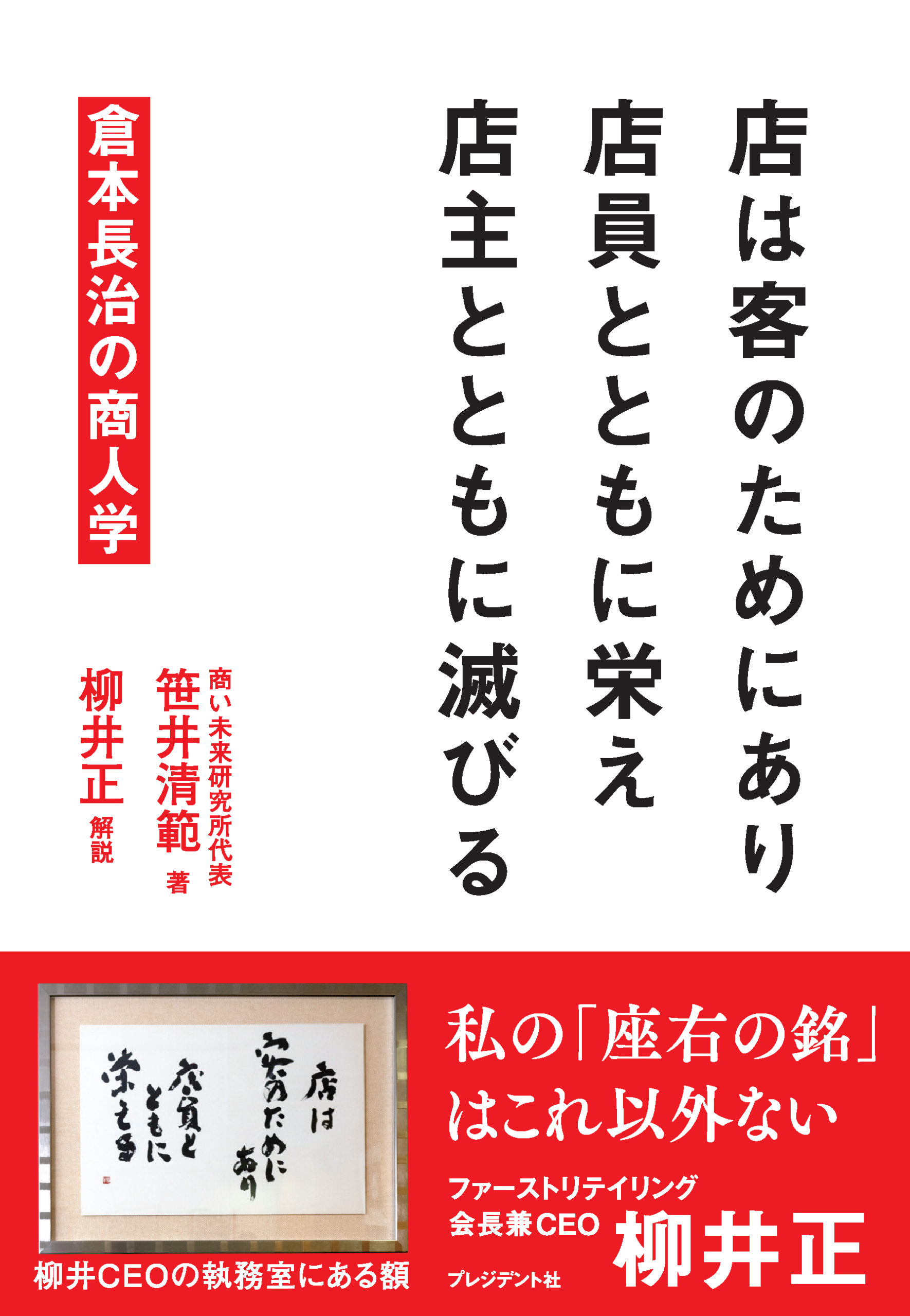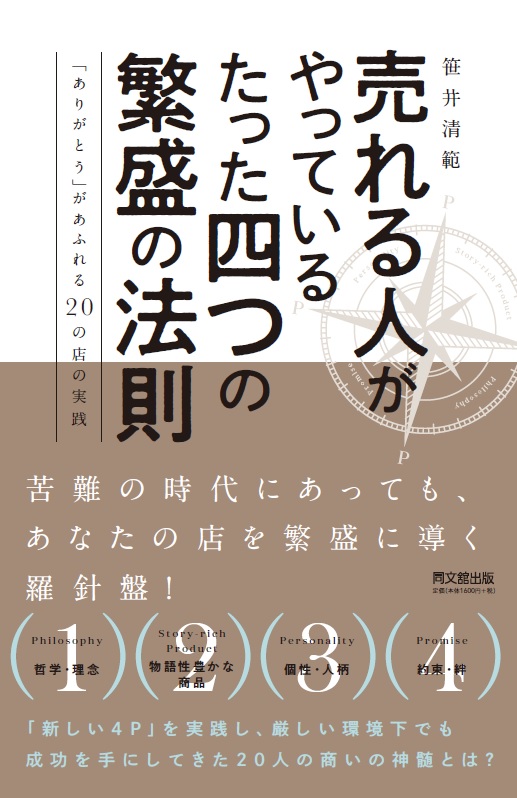「わかりました」
商いの現場でも、会議でも、研修でも、私たちはこの言葉を頻繁に使います。しかし、その一言の中に含まれる「わかる」はどの程度の深さでしょうか。
売上不振の原因が「わかった」。
お客さまの声の大切さが「わかった」。
この店の強みが「わかった」。
そう言いながら行動が変わらない場面を、私たちは何度も見てきました。それは、本人が怠けているからではありません。「わかる」の段階が途中で止まっているだけなのです。
四つの「わかる」で異なる理解の深さ
「わかる」と読む漢字には、意味も役割も異なる表現があります。それらを意識して使い分けることは、言葉の問題ではなく、思考の深さを測る物差しになります。
分かる――全体像が見えた理解の“入口”
「分かる」はもっとも一般的で、もっとも使われる表記です。話の要点がつかめた、全体像が見えた、という状態を表します。たとえば、ある商店街での勉強会。講師の話を聞き終えた参加者がこう言います。
「なるほど、集客には“理由”が必要なんですね。よく分かりました」
これは、決して否定されるべき反応ではありません。相手の話を受け止め、理解しようとした証です。ただし、この段階では、まだ何も変わっていません。
なぜなら、「分かる」は輪郭が見えただけだからです。その理由をどうつくるのか、自分の店では何を変えるのか、そこまではまだ踏み込んでいません。「分かる」は理解のゴールではなく、スタート地点です。
「判る」――やる・やらないが決まった“決断”の理解
次の段階が「判る」です。これは、判断がついた状態を意味します。同じ勉強会のあと、別の店主がこう言います。
「うちの店は、新規客より常連づくりに力を入れるべきだと判りました。だからチラシはやめて、顧客名簿づくりを始めます」
ここではじめて、理解が行動の方向性を持ちます。選択と集中が生まれています。商いでは「全部大事」「どれも必要」と言っている限り、何も決まりません。「これはやる」「これはやらない」と線を引いたとき、理解は「判る」という段階に進みます。
理解しているのに決断できないということもあります。それは「分かっているが、判っていない」状態です。成果を分けるのは能力よりも、この一線です。
「解る」――理由を説明できる“構造”の理解
「解る」は、なぜそう判断したのかを言葉で説明できる理解です。先ほどの店主が、スタッフにこう話します。
「チラシ集客は一時的には来店が増えるけれど、価格目的のお客さまが多く、定着しにくい。一方、常連さんは客単価が高く、紹介も生んでくれる。だから、うちは名簿づくりに力を入れる」
ここでは因果関係が整理されています。これは再現性のある理解です。「解る」段階に達すると、人に伝えることができ、振り返りができ、改善ができます。商いが「属人芸」から「共有知」へ変わります。組織で商いを続けるために、極めて重要な理解です。
「了る」――引き受けると決めた“覚悟”の理解
そして最後が「了る(わかる)」です。現代ではほとんど使われませんが、意味としては最も深い用法です。同じ店主がある夜、帳簿を見ながらこう思います。
「正直、不安はある。名簿づくりも、接客も、手間は増える。すぐに成果が出る保証もない。それでも、このやり方で行こう」
これが「了る」です。条件が完璧にそろっていなくても、正解かどうか分からなくても、自分が引き受けると決めた理解。商いの現場で問われるのは、常にこの覚悟です。誰かが責任を取ってくれるわけではありません。だからこそ、「了った」という感覚が、最後の支えになります。
本当に「わかる」とは何か
整理すると、理解には段階があります。
分かる:全体像が見えた
判る:やる・やらないが決まった
解る:理由を説明できる
了る:覚悟として引き受けた
多くの人は「分かる」で止まります。優秀な人は「解る」まで進みます。そして、成果を出し続ける人は、必ず「了る」まで行っています。
会議のあと、研修のあと、失敗のあと、「今回はどこまでわかったのか」と自分に問い直してみてください。理解の段階を言葉で区別できるようになると、思考は自然と深くなります。言葉を選ぶことは、思考を選ぶこと。「わかる」を使い分ける人は、理解の浅瀬に立ち止まりません。
本当に「わかる」とは、頭で理解し、判断し、説明し、そして覚悟として引き受けた状態のことです。その積み重ねが、商いの質を、人生の納得度を静かに、しかし確実に高めていくのです。