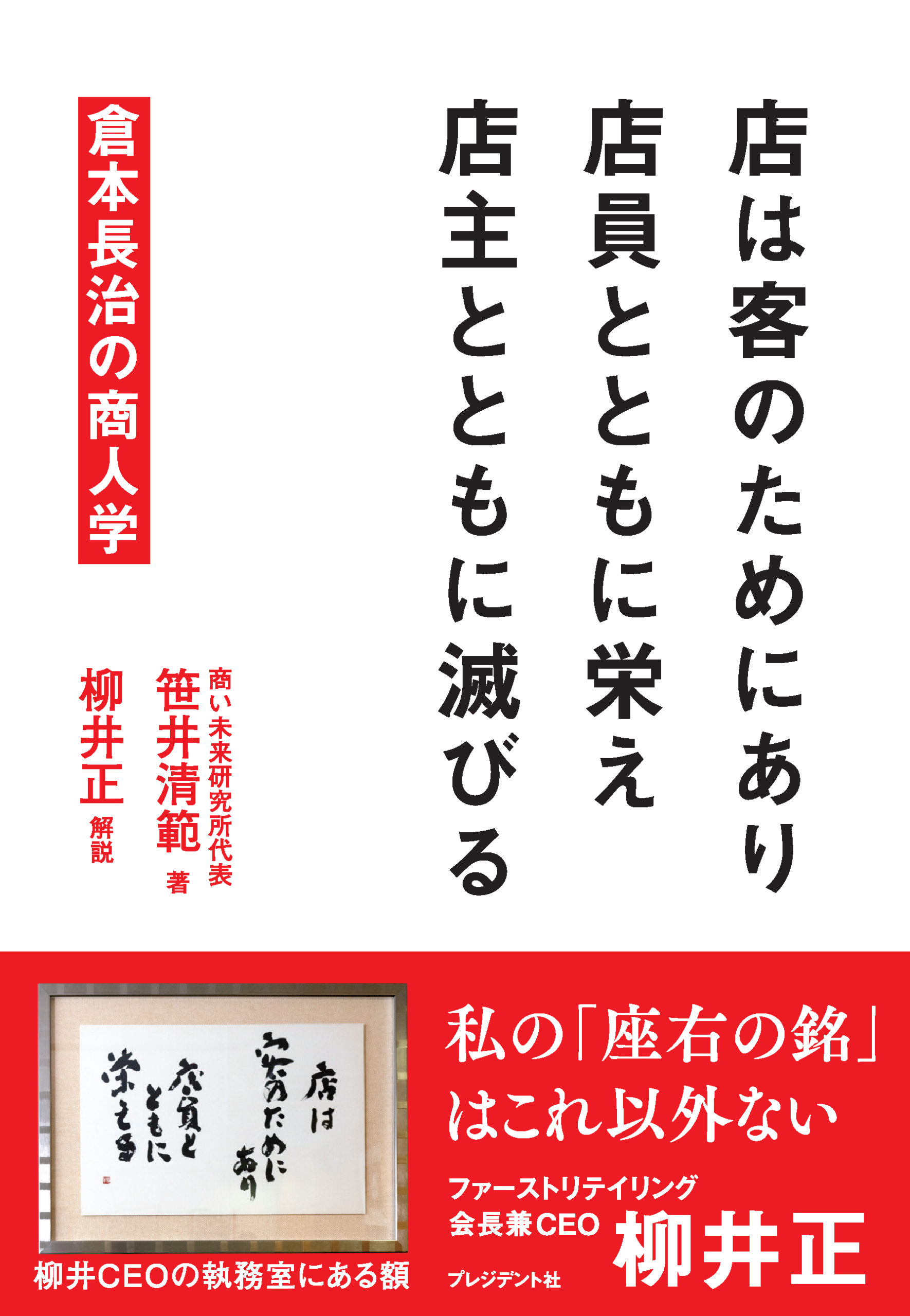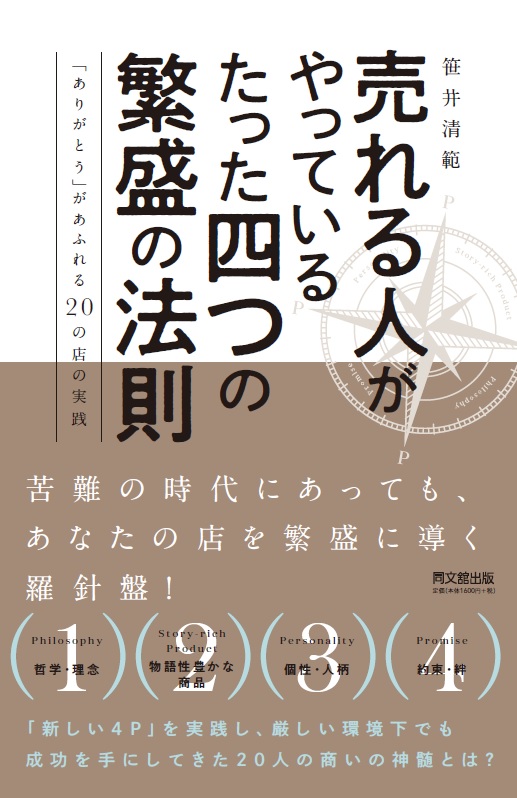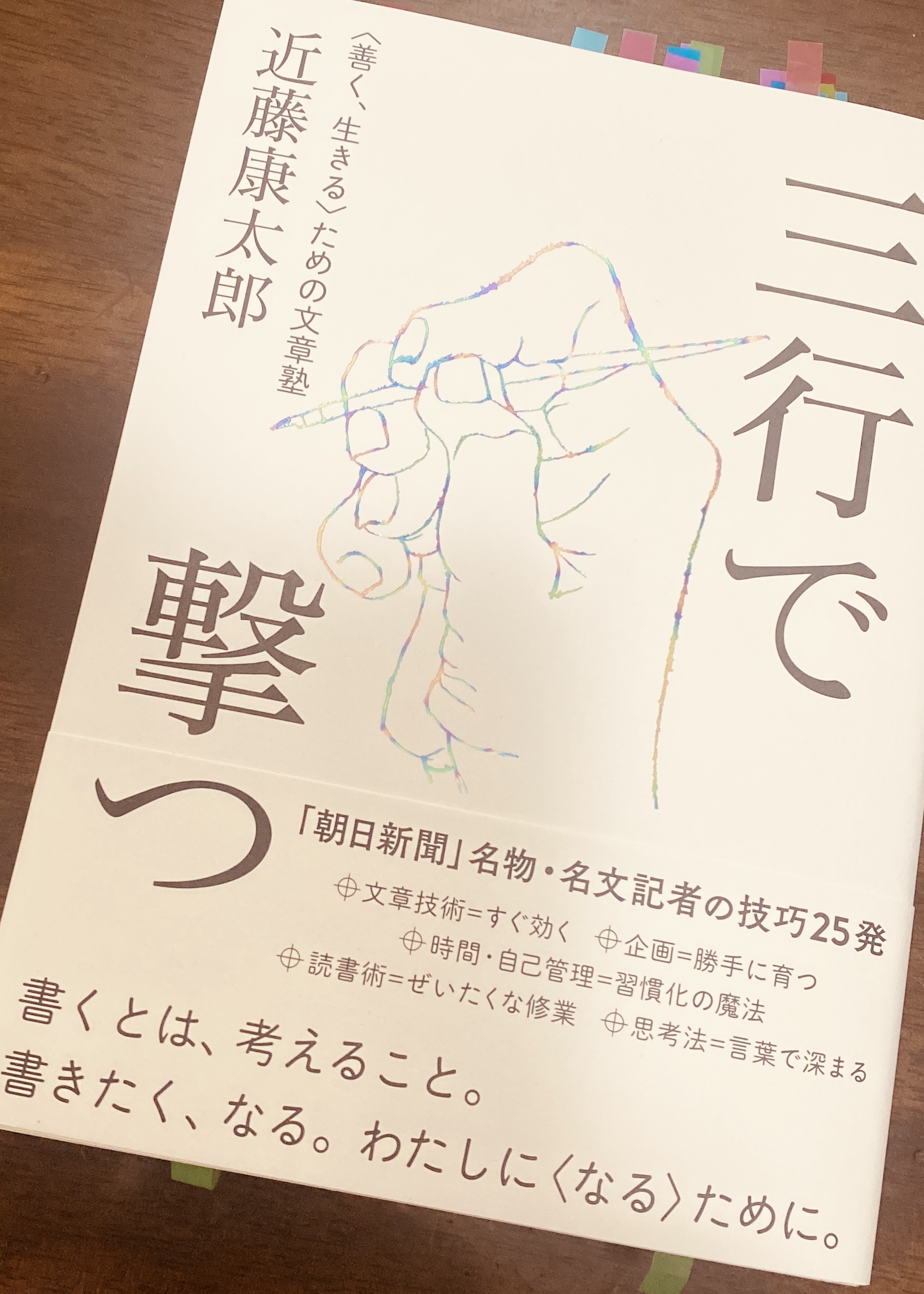仕事部屋の机から、ふと目を上げた先に一枚の額があります。そこに掲げられているのは、商業界創立者・倉本長治が揮毫した「眞」という一字です。ずいぶん前、恩人から授かったものですが、今では私の仕事と人生の“軸”のような存在になっています。
日々の仕事に追われ、判断に迷い、言葉に詰まるとき。無意識のうちにその一字に目が向かい、「さて、自分はいま何に立っているのか」と問い直している自分がいます。
「真」という字は、あまりに簡単で、あまりに重い。だからこそ、折々に見つめ直す価値があります。今日はこの一字をテーマに、商人として、仕事人としての信念について考えてみたいと思います。
真とは「正しさ」ではない
「真」と聞くと、多くの人は「正しいこと」「間違っていないこと」を思い浮かべるでしょう。しかし、現場で仕事をしていると、正解が一つに定まらない場面ばかりに出会います。
価格を上げるべきか、据え置くべきか。
人を雇うべきか、身の丈に合わせるべきか。
顧客の要望に応えるべきか、断るべきか。
そのどれもに「絶対的な正解」はありません。では、「真」とは何なのか。私がこの一字を見つめ続けてたどり着いたのは、真とは正解であることよりも、ごまかさないことではないかという考えです。
数字をよく見せるために都合の悪い事実を隠していないか。忙しさを理由に、向き合うべき相手から目を逸らしていないか。「仕方がない」という言葉で、自分の判断を正当化していないか。真であるとは、立派であることではありません。弱さや迷いを含めて、「自分はいま、こう考えている」と引き受ける姿勢のことだと思うのです。
倉本長治が説いた商人の道も、決して理想論ではありませんでした。現実の厳しさを直視し、そのうえで誠実であろうとする覚悟。その覚悟の核心に、「真」という一字があるように思えてなりません。
信念とは声高に語るものではない
「信念がありますか」と問われると、どこか気恥ずかしさを覚える人は少なくありません。信念という言葉はあまりに大きく、立派に聞こえるからです。しかし、信念は掲げるものではなく、日々の判断に滲み出るものではないでしょうか。
たとえば、利益が出ない仕事でも約束だからと引き受ける、効率は悪いが顧客にとって必要な説明を省かない、短期的に楽な選択より長く続く道を選ぶ――そうした一つひとつの選択に、その人の「真」が現れます。
私自身、取材や講演を通じて数多くの商人と向き合ってきました。長く続いている店、信頼を集めている経営者には共通点があります。それは、「この人は、どこで線を引くかがはっきりしている」ということです。やらないこと、譲らないこと、守り続けることが明確なのです。
その基準は、派手な理念として語られることはありません。むしろ静かで、控えめで、しかし揺らがない。まさに「真」という字が放つ佇まいそのものです。
信念とは、困ったときにこそ試されます。都合が悪くなったとき、損をするとわかったとき、それでも同じ判断ができるか。その積み重ねが仕事の信用をつくり、人の評価をつくっていきます。
自分なりの「真」を見つめ直す
忙しい日々のなかで、人はどうしても目の前のことに追われます。メール、会議、締切、数字、トラブル。気づけば、「なぜこの仕事をしているのか」を考える余裕を失ってしまいます。
だからこそ、意識的に“立ち止まる装置”が必要です。私にとって、それが机の先にある「眞」の一字です。何かを決める前に、ふと見上げます。そこに、答えが書いてあるわけではありません。ただ、「ごまかしていないか」「逃げていないか」と、問いを投げ返してきます。
不思議なことに、その問いに向き合うだけで判断が整うことがあります。すぐに答えが出なくても、「この方向で間違っていない」という感覚が残ります。それで十分なのだと思います。商いにおいて、最も怖いのは失敗ではありません。自分でも理由がわからないまま、流されて判断してしまうことです。
「真」という一字は、私にとって羅針盤です。進む道を示すのではなく、北を見失っていないかを確かめるための印。派手さはなくとも、毎日そこにある。それが、信念を信念たらしめる条件なのかもしれません。
仕事に迷いが生じたとき、判断に自信が持てなくなったとき、一度立ち止まり、自分なりの「真」を見つめ直してみる。その静かな時間こそが商人をぶれさせず、仕事を長く続けさせる力になる。私はそう信じています。