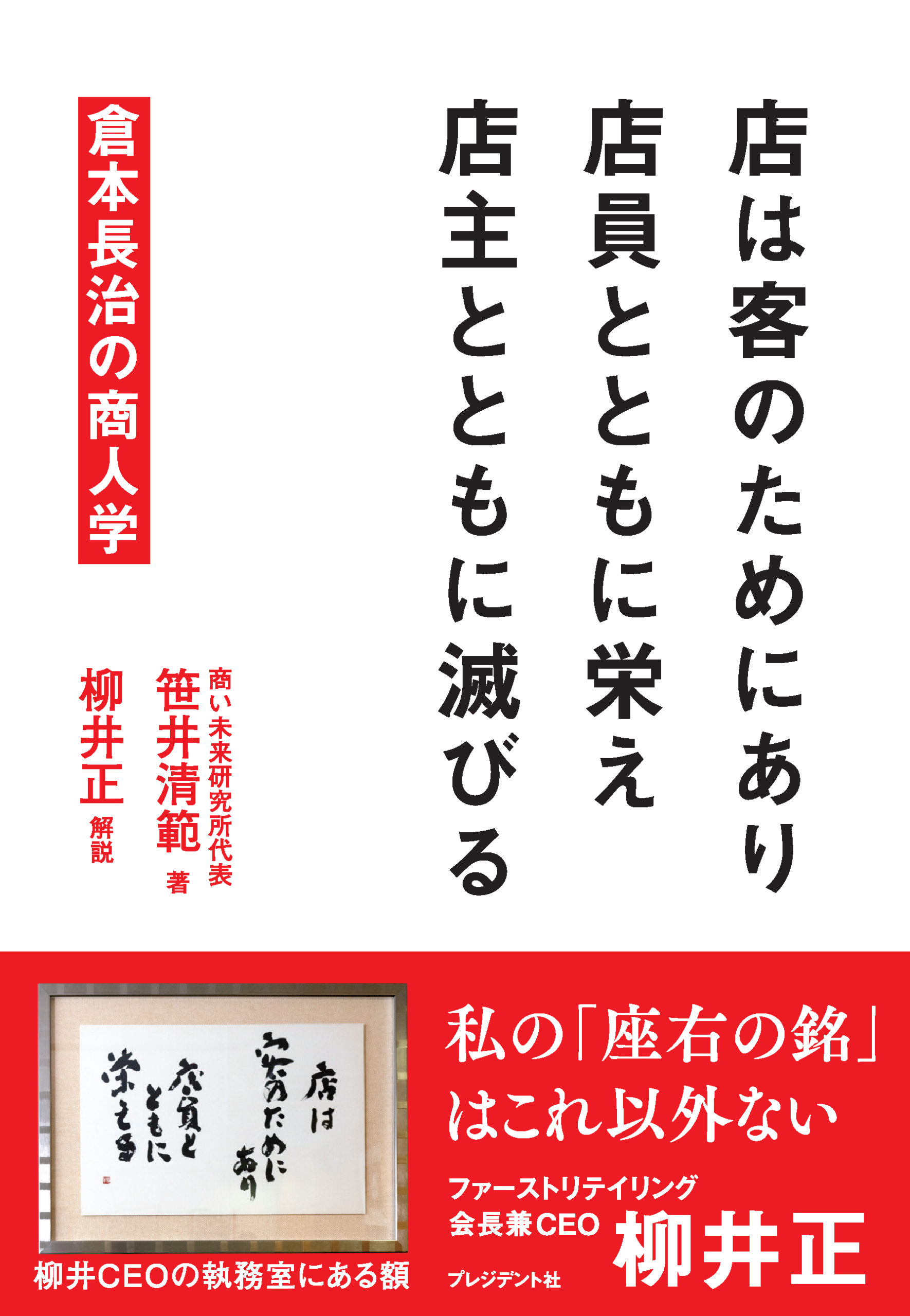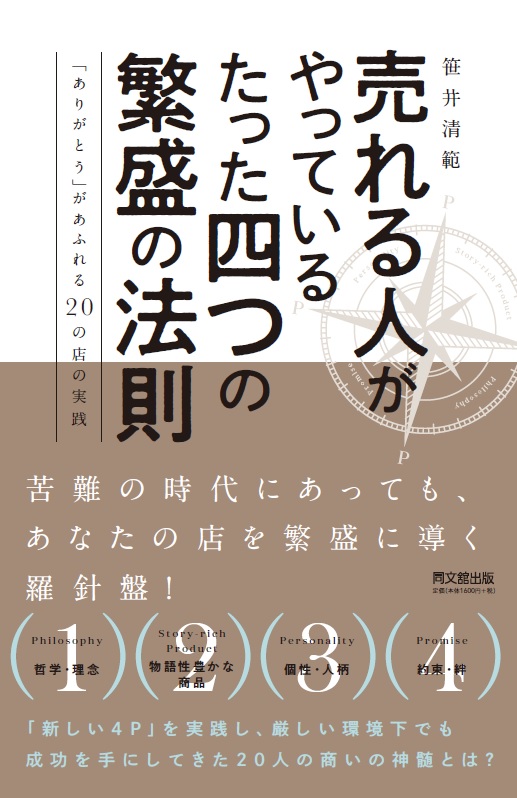「良い商品なのに売れない」
「理屈では説明できない買われ方をする」
商いの現場に長く立っている人ほど、こうした経験を数え切れないほど持っています。行動経済学は、まさにその違和感から生まれた学問です。
従来の経済学は、人を「合理的に判断する存在」と仮定してきました。価格と品質を比較し、もっとも得な選択をする――。しかし現実の人間は、そうは動きません。
「なんとなく不安で決められない」
「後悔しそうな選択を避ける」
「周りの人の選択に影響される」
「面倒になると判断を先送りする」
行動経済学は、こうした人間の非合理さを否定せず、そのまま研究対象にした学問です。つまり、「人は弱く、迷い、感情で動く存在である」という前提に立った、きわめて現実的な学問なのです。
この前提は、商いと非常に相性がいい。なぜなら、店に来るお客さまもまた、迷いながら、感情を抱えながら売場に立っているからです。
人は「失敗したくない」
行動経済学を理解するうえで、もっとも重要な視点の一つがあります。それは、人は得をしたい以上に、損をしたくないということです。
これは多くの実験や研究で繰り返し示されてきました。同じ価値であっても、「得られる喜び」より「失う不安」のほうが、心理的な影響は大きい。この性質は、売場にそのまま現れます。
「選択肢が多いと決められない」
「高額になるほど慎重になる」
「『本当にこれでいいのか』と迷い続ける」
ここで商人が陥りがちな誤解があります。「説明が足りないから決まらない」「もっと説得しなければならない」と思ってしまうことです。しかし実際には、説明不足ではなく、決断の負担が重すぎることが原因である場合が少なくありません。
行動経済学の視点に立てば、商人の役割は変わります。説得する人ではなく、迷いを減らす人になるのです。
選択の責任を分かち合う
行動経済学では、人は判断に伴う責任を嫌うことが知られています。「自分で決めた」という事実が、失敗したときの痛みを大きくするからです。だからこそ、人は無意識のうちに、「多くの人が選んでいるもの」「店が勧めているもの」「定番と書かれたものに安心感を覚えます。
ここで重要なのは、「一番売りたいものを押し付ける」ことではありません。「初めての方にはこちらが多いです」「迷われる方は、まずこれを選ばれます」という言葉は、判断を奪うのではなく、判断の重さを分け合う行為です。行動経済学を活かす商いとは、お客さまの選択を操作することではなく、選択に伴う不安を、商人が引き受けることなのです。
価格は「意味」で受け止められる
行動経済学は、価格の受け止められ方についても、多くの示唆を与えてくれます。人は、価格そのものを評価しているようで、実は価格の背景にある意味を評価しています。
同じ値上げでも、「黙って上がった価格」と「理由が語られた価格」では、受け止めはまったく異なります。重要なのは、安く見せることではありません。「なぜこの価格なのか」を、商人自身が腹落ちして語れるかどうかです。
行動経済学は、値付けをテクニックに変える学問ではなく、値付けを覚悟に変える学問だと言ってもいい。語れない価格は、不安を生みます。語れる価格は、納得と信頼を生みます。
行動経済学が教える商人の誠実さ
行動経済学というと、「人を動かす心理テクニック」「売るための裏技」と誤解されることがあります。しかし、本質はまったく逆です。人は合理的ではありません。だからこそ、誇張すれば裏切られ、煽れば警戒され、一度失った信頼は簡単には戻らないのです。
また、行動経済学は、人の弱さを利用する学問ではありません。人の弱さを理解したうえで、どう誠実でいられるかを考える学問です。迷う人の隣に立ち、決めきれない気持ちを急かさず、「ここで選んでよかった」と思える体験を整える。それこそが、商いに行動経済学を活かすということです。
商いは、人を相手にする仕事です。人は、揺れます。迷います。後悔を恐れます。行動経済学は、その揺らぎを欠点とは見ません。むしろ、商いが寄り添うべき現実として捉えます。
理屈よりも、関係性。説得よりも、安心。行動経済学は、商人が「売る人」である前に、「人を理解し続ける人」であることを、静かに教えてくれるのです。